シベリアの川を船で旅する観光船の事業で成功を収めていた事業家のウラジーミル・メグレは、樹齢何百年も経た大木の針葉樹が生い茂るタイガの森の奥で、アナスタシアという美しい女性と会う。
ほとんど文明と接触したことがないにもかかわらず、野生的というよりは自然そのものにみなぎる優雅さをたたえている。その知識、特に哲学的な思索は驚くべきもので、私たちの文明の問題点も鋭く見据えている。
彼女によると、ローマに征服され、キリスト教化される前には、ヨーロッパ全域を中心に、インドや中国といったユーラシア大陸全体に「ヴェーディアン」と呼ばれる文明が広がっていた。キリスト教化とともにその後、ヨーロッパに広がった文明は、ヴェーディアンの力を恐れて、その記録を徹底的に抹消し、「異端」「魔女」といったレッテルの下、迫害してきた。でも、奥深い森など、彼らの手の届かないところに逃れることで、生き延び、その精神を、そのまま受け継ぎながら、生きてきた人たちも少なからずいる。彼女はその末裔の一人なのだとか。
古い文明を受け継ぐ彼女の一族のような人々は、自然の力を引き出し、あやつる智慧に優れていたために、主流文明と接触し、助けることも、歴史上、何度かあった。でも、その力を独占しようと幽閉されて、彼ら自身は夢にも考えたことのないような、私利私欲、権力欲につかえる道具にされたり、魔女として恐れられ、火あぶりにされることも少なくなかったという。彼女の一族で、主流文明の中へと入っていった人たちは、一人残らず、不慮の死を遂げたという。
そんな恐るべき知識や能力を持ちながらも、彼らはそれを、あくまで、自然に溶けこみ、一体化した暮らしから引き出している。だから彼らは今も、人工物はほとんど作らず、もたずのシンプルな生活を送っているので、自然の中の彼らの住処を訪れても、他の場所よりきれいだな・・・・と思うだけで、人がそこに住んでいるとは普通、夢にも思わないのだという。実際、アナスタシアの住処も、ただ、松の樹に囲まれた草原があるだけ。ただ、そこにある大きな樹の穴を覗くと、干した苔やハーブを敷いた、暖かく、いい香りの立ち込める寝床がある。
そのアナスタシアから聞いた話を、ウラジーミルは、1巻目の『アナスタシア』を皮切りに、10冊にわたる本にしたためた。
記憶のたび

私は両親とも南の福岡出身。ロシア人の血が混ざってる可能性はまずない。にもかかわらず、『アナスタシア』にはじまる『響き渡るシベリア杉の木』シリーズは、読めば読むほど、DNAに描きこまれた記憶の古巣を覗き込んでいるような不思議な気持ちがしてくる。多分人類共通の記憶に触れているのだろう。
たとえば・・・
彼女の動物たちとの深いつながり。松の実の皮を剥いたものを口に運んでくれるリスに優しい声をかけながら触れると、リスはしばらく恍惚状態で、電気に打たれたようにしばらくじっとしている。
個人的な関係を育みながら、愛情深く育てられた植物は、その人に必要なエネルギーを天空と大地から集めることで、お返しをすること。
彼女がその末裔として、その文化の多くを継承しているという古代の民族、ヴェーディアンの人たちは、着る人が不運から守られるように、服に刺繍をほどこす方法を知っていたこと。
そもそも、まわりの空間に愛を放射するような生活を送り、
一挙一動に、触れるすべてのものに愛を注ぎこむことで、
そこにいる人が庇護されていると感じ、
本領を発揮できる場所をつくることができる。
それが本当のふるさとであり、家。
そんな場所をつくるのに必要なのは、愛情だけで、人工的なものは、本当に、何もいらないこと・・・
そういう話が満載されたこれらの本を読み進むにつれ、「そんな生活、私、知ってる!」と思うのだけど、どうしてそう思うのか、いつの記憶なのか、わからない。わかるのは、それがとってもなつかしい、でも遠い日のことだってことだけだ。
いのち生かしたままのものづくり

そうした話の一つ一つは、もちろん、とても非合理的に見える。
それも、もっともな理由があってこそ。
死んだものを相手にした時ならば、私たちはいくらでも合理的になれる。
実際現代の人間は、どんなに生きたものも、分析し、分解し、あらかじめ殺してから、組み立てようとする。
実際、主人公のアナスタシアに言わせると、現代の人間の創造性のほとんどは、そうした、死んだものを材料にしたものづくりに当てられているという。
でも、そうやって、どんなに完璧で「合理的な」人工の世界をつくりあげても、それで、生きたものをつくりだすことは、できない。
生き物の身体を、部分部分に分解したあと、どんなに完璧に正しく組み合わせ、縫合しても、死んだ生き物は、息は吹き返すことができないのと同じことだ。
だから、私たちのつくった人工物(機械がその代表例)には、
生きているものにだったらどんなものにも必ずある再生力や自浄力、内発的なエネルギー源が欠けている。
死んだものは生きたものと違い、内発的なエネルギーを持たないから、外から化石燃料を注入しなきゃいけない。
これはもちろん、汚染をすすめる。それに加えて、新陳代謝による自浄・再生力も持たないから、汚れれば、汚れっぱなし。
また、放っておくと古び、朽ちていくものを何とか維持するのに途方もないエネルギーやリソース、労力を傾けなきゃいけない。
つまり、メンテナンスが大変だ。
すべての環境破壊や汚染のおおもとは、私たちが死んだものを材料にした創造しか行わなくなったことにあると、考えられる。
つまり、合理的に見えて非合理的。先端的に見えて原始的。
放って置かれた家は、どんどん傷んで、荒れていく。その一方、傍の庭木ばかりは、力強く、つややかに青々と生い茂り、大きく成長しているのを見かけることがあるのは、皆さん、ご存知の通り。
それこそ、人工物は最小限にして、生きたものに寄り添って、その生命に包まれるようにして生きていけというのが、神の意志だってことをはっきりあらわしてはいないだろうか。
何よりアナスタシアを悲しませるのは、そんな死んだ人工物の原材料として、多くの場合、生命のある、完璧な美しさをたたえたものが、冷徹な手で殺されてしまうことだった。
「(・・・)君は何かを創造できるかい? たとえば刺繍ぐらいはで きるのかい? 布に針で美しい図案を刺繍できるかい?」
「私は刺繍できなかった」
「どうして?」
「針を持てなかったから。針は生きている自然の深みから作り出されている。何かを創るために、まずは、大切な生きている創造物を破壊しなければならないのなら、どうしてつくれるというの? ウラジーミル、誰か愚かな人が、偉大な画家——あなたの言う創造者——が描いた油絵の画布をナイフで切って、その画布の切れ端から小さなウサギや人間の形を切りだしていったと創造してみて。その愚かさを無視するとして、彼のこの行動は創造性の現れだと呼べる? でも、知的で、ものごとをよくわきまえている人(自称芸術家?堀田)が同じことをしたら、彼の行動にはちがった定義づけがなされる」
「なんだって?」
「これについて一緒に考えてみましょう。たとえば、彼の行動はバンダリズム、芸術作品の破壊行動とよばれるかもしれないわ」
(『愛の空間』289ページ)
ようするに、生きた存在を殺さず、生きたまま、人に恵みをもたらすようにするのが、アナスタシアがよしとする仕事らしい。
たとえば、機械を使う代わりに、動植物といい関係をつくって、彼らに助けてもらう。
未邦訳の10巻、『アナスタ』には、アナスタシアとウラジーミルの二番目の子供、アナスタの前世のエピソードとして、動物たちに家づくりを手伝ってもらう古代の人々の話さえ出てくる。
マスターするのが難しい独特の口笛の調子をさまざまに変えながら、クマを呼び出し、柱を立てるための穴を掘ってもらい、マンモスに石を運んできてもらったり、無数のツバメたちに、くちばしに泥や藁を加えてきてもらって、土壁をつくらせる。
もちろんそんなふうに、動物をあやつったり、アナスタシアのように、リスにナッツの殻をむいてもらうのは自然界からずいぶん離れてしまった今の人たちには、ちとハードルが高いもの。
とはいえ、合鴨農法の合鴨の使い方は、かなりいい線いっているのではないかと思う(動物を単なる道具と見なしてるようなところ、とくに、働き終わって用済みになった合鴨をたべてしまつところは、ちょっといただけないと思うけれど)。
その他もろもろの自然と調和した農業やガーデニングも、私たちの時代に残る生命を生かしたままのものづくりの例だっていえる。
生きた動物と愛情深い関係を育みながら、助け合い、生きていく。その様子は、メルヘンのような詩情をたたえ、懐かしい気持ちで私たちを満たす。
たとえば、先ほど述べた、アナスタの家づくりの話。熊やマンモスやツバメの手をかりるのは、当時家を建てる人は誰でもやっていた慣行的な建築法だったけれど、アナスタはこれに飽き足らず、自分の家のデザインに、斬新で詩的情緒ゆたかなアイデアを加えた。それは次の通り。
彼女の家の南向きの屋根の下に、蜂の巣箱を置く。すると、ちょうどミツバチが花粉を巣に集めてきたころ、そこに日が差し込んで、巣は暑くなる。
すると、ミツバチたちは、巣の温度を下げようと、羽を振動させて、風を巣箱に送り出す。すると、花粉が発する花々のいい香りが、家の中に流れこんでいく。
面白いのは、それがどんなに斬新でも、生きたものを生きたまま使うところは、変わらないことだ。
相手が「人間」という生きたものとなると、私たちの時代も、生きたままつくる仕事の例もぐっと増える。
これは「ものづくり」というより、育児、教育、治療と呼ばれるけれど。
アナスタシアがなぜ、菜園づくりと子育てと癒しの話ばかりするのかも、これで納得がいくというもの。
私たちの世界にあるそれ以外の仕事は、たいてい、生きたものを切り刻み、一から組み立て直す。屍の上に成り立ってるからだ。
*
しかし、すべての偉大な芸術家の努力がまったく無駄だったなんて、ちと極端すぎやしないか? そう抗議するウラジーミルに、アナスタシアは次のように答えている。
「彼らには彼らのレベルでの宇宙に対する気づきがあり、そのレベルにおいては画家であり、創造者よ。でも、もし彼らがもうひとつ別のレベルでの気づきを得たら、彼らの創造するものは、もっとちがった方法で生み出される」
「どんな方法だい?」
「創造主がインスピレーションのほとばしる中で、すべてのものを創造するときに用いられた方法よ。神は、ご自身の創造を完成し、さらに新たなものを創造する能力を人間に与えられた。人間だけに」
「創造主はどうやってすべてのものを創造したんだい? そして彼は人間にどんな道具を創造のために与えたんだい?」
「意識が、偉大な創造主の主要な道具よ。そして人間にはその意識が与えられている。魂と直感と感情、そして最も大切なものである気づきの純粋性、これらに意識が呼応したときに創造が起こる」(『愛の空間』)
意識による創造といっても、それだけだと、抽象的で、イメージしにくいけれど、このすぐ後で、アナスタシアがその実演をする場面がある。
「見て、花があなたの足元に咲いている。その形も色も美しい。それらは生きた創造活動の中で、ハーフトーンの色合いで変化する。さあ、あなたの意識でそれをさらに改善してみて。集中して。もっと美しい姿に変えて」
「どんなふうに? たとえば」
「自分で想像してみて、ウラジーミル」
「ああ、想像してみよう。たとえば、このフランスギクは、花びらの一枚を赤くして残りは今のままにしたり、それが交互になったりしたら、もっときれいで楽しくなると思う」
突然アナスタシアはまったく動かなくなった。彼女は顔を近づけて白いフランスギクをじっと見つめはじめた。すると、静かにゆっくりと、二人の目の前で、フランスギクは花びらの色を変えた。今や、赤、白、赤と、交互になっている。赤い花びらははじめはかすかに赤い程度だったが、それから、どんどん赤くなり、最後には燃えるような赤となって輝いた。
「ほら、このとおり、あなたが想ったとおりになったし、私は私の意識ですべてを生み出した」
「こういうことは誰でもできるって言うのかい?」
「そうよ! そして彼らはやっている。でも、彼らは殺した材料を用いている。死んでいるものは分解していくだけ。こうして人間は何世紀もわたって、自分たちが想像したものの分解や腐敗をくい止めるために闘ってきた。だから、人間の意識はますます腐敗の方へ向けられ、真実の創造がどうあるべきかについて想いをめぐらす時間がない」(『愛の空間』)
私たちの世界で生命をいかしたままのものづくりをする人の方はもちろん、
アナスタシアのように「意識」の力だけで、デイジーの色を変えたりと、対象の姿を変化させるところまではなかかないかない。
けれど、たとえば、植物を見事に育て、美しく開花させたり、たわわに実らせたり、
とびっきり美味しい野菜をつくったり、
素晴らしい景観に生命力があふれるガーデンをつくったり、
病気を癒したり、問題を抱えた子供たちを立派にしだてあげると言った
生命を生かしたま、生命をあやつる、これらのデリケートな仕事をうまく成し遂げるには、
愛情や気遣い、想像力といった「意識」がとっても大切だという点は、
私たちの世界の仕事も、変わらない。
何と言っても、これらの仕事は、死んだものを材料にするのと比べて、地球をこれ以上人工物で埋め尽くしたり、ゴミや汚染物を比較的出さなくて済む。
化石燃料より新陳代謝のエネルギーを使うし。そんな、地球に優しいところもいい。
結局彼女のメッセージはとてもシンプルだ。
地上の生命を殺したり、その本来の力を骨抜きにして、単なる物にしてから、一から組み立て直す下手な人工物で地上をうめつくすかわりに、
生きたまんまのものを増殖させ、その生命をますます健やかにし、本来の能力を全開させながら、人間もこれを楽しみ、恵みを味あわせてもらいながら、共栄共存。
地球を健やかで生命とよろこびあふれる星にするのが、私たち人間の本来の役目だということ。
アナスタシアはこれを、生命の源泉である「神」との「共同の創造」と呼ぶ。
続きを読みたい方は、ここをクリックしてください。
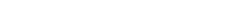

最近のコメント