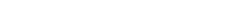私は両親とも南の福岡出身。ロシア人の血が混ざってる可能性はまずない。にもかかわらず、『アナスタシア』にはじま『響き渡るシベリア杉の木』シリーズは、読めば読むほど、DNAに描きこまれた記憶の古巣を覗き込んでいるような不思議な気持ちがしてくる。多分人類共通の記憶に触れているのだろう。
たとえば、彼女の動物たちとの深いつながり。松の実の皮を剥いたものを口に運んでくれるリスに優しい声をかけながら触れると、リスはしばらく恍惚状態で、電気に打たれたようにしばらくじっとしている。
個人的な関係を育みながら、愛情深く育てられた植物は、その人に必要なエネルギーを天空と大地から集めることで、お返しをすること。
彼女がその末裔として、その文化の多くを継承しているという古代の民族、ヴェド文化の人たちは、着る人が不運から守られるように、服に刺繍をほどこす方法を知っていたこと。
そういう話が満載されたこれらの本を読み進むにつれ、「そんな生活、私、知ってる!」と思うのだけど、どうしてそう思うのか、いつの記憶なのか、わからない。わかるのは、それがとってもなつかしい、遠い日のことだってことだけだ。
たましいで生きると世界が近づいてくる
この既視感は一体、どこからくるのだろう?
それは一言で言えば、周囲の世界を信頼しきって、安らいでた頃の記憶だ。
メス狼は、人間の赤ちゃんを見つけると、自分の子と一緒に乳を飲ませ、育てる。けれど、大人の人間に出会うと八つ裂きにしようとするのはなぜか。『新しい文明 愛の儀式』の中で、アナスタシアの祖父は言う。人間の側の恐怖心と、そこからくる防衛的な構え、攻撃性を、狼は敏感に察知して、同じように攻撃体勢に出るのだ。
つまり、周りの世界は私たちの鏡。母の胸に抱かれる赤ちゃんのように、周りのものを、人生を信頼しきって、「大丈夫」と、そこに自分を安心してゆだねきることができるとき、動物たちが、自然が、人が、世界が近づいてくる。
リスに木の実を剥いてもらい、狼や熊に育児を手伝ってもらうアナスタシアやその一族は、この信頼感、攻撃性のなさに欠けては、赤ちゃんの境地をずっと保ってるといえるのかもしれない。
私たちにもそれは、できるはず。だって私たちも、一度は赤ちゃんだったのだから。アナスタシアの住む草原に繰り広げられるこの動物たちとの融和の話を聞いて、懐かしい気持ちにひたされるのだから・・・
でも、物心ついたあとにも、近く狼や熊に対して、全く恐怖心を抱かないなんて、実際問題として不可能でしょう? と言われるかも。
身体は死んでも残る不滅の部分、絶対に傷つかないたましいに意識の焦点がぴたっと合っていて、身体を度外視できるようになれば、何とかなるかも。
アナスタシアがたましいについて気づいたのは、「地球を抱きしめるにはどうすればいい?」というおじいさんの質問に答えようと、一生懸命考えていたときだった。
そのとき彼女にひらめいたのは、彼女の草原にいる動物たちは、彼女が遠くから愛情こめて眺めるだけで、直接撫でられた時と同じように、うれしそうに尻尾を振ることだった。これはつまり、彼女の見えない身体で撫でてるから。この見えない身体は伸縮自在、これでだったら、地球みたいに巨大なものだって、抱きしめられる。
そう答えた時、おじいさんはアナスタシアに、「それをたましいと呼びなさい」と言ったのだった。
正直言って私も、森で熊にあっても、こわがらずにいられるか、まだ自信はない。ただ一つ思うのは、そんなときには、まず、この「たましい」で、先に熊を抱きしめようってこと。
普段から、練習しておく必要も、あると思う。あらゆる「こわい」って思うあらゆるものを、「たましい」で抱きしめ、あたため、それも実は自分と一つだってことを確認しては、安心する。そんな修行を重ねていたいって思うんだ。
そんなふうに、すべてを一つにつなぐたましいでふんわり包み、包まれながら、世界に対する信頼感、安心感をとりもどす。それにつれ、ものの見方が変わり、やさしさ、なつかしさ、光で満たされてくる。
愛のエネルギー
攻撃性をなくすとは、単に暴力に訴えないことにとどまらない。攻撃する必要がないのは、こわがらないから。こわがる必要がないのは、安心しているから。安心しているのは、たましいは一体であることを知っているから。生きとしいけるものをつなぐ一つにつなぐ、このたましいが感じられたら、どんな人も、よろこびのあまり武器を捨てるって確信しているから・・・そんなふうにつきつめていくと、自然に愛のエネルギーが周りに放射されるようになる。
全く無防備になりきったときにみなぎってくる愛のエネルギー。これが放射されるようになれば、これこそが、今度は、武器の代わりに、その人を守ってくれるようになる。
といっても、それはもちろん物理的な暴力も遮断し跳ね返す防衛力のかたちで守ってくれるのではない。どんな荒ぶれた心も宥め、よろこびに溶かしてしまう融和力、生きとし生けるものを一つにつなぐその力で守ってくれるんだ。
モーツアルトの『魔笛』で、主人公が森の動物たちに襲われそうになったとき、笛を吹き始めたときに起こったことと同じ。主人公の笛の音に動物たちは攻撃しようとしていたことも忘れ、よろこびのあまり踊り始めた。その様子に似てる。
非暴力に徹するから愛のエネルギーを周りに放射するようになる。すると、それが周りの人や動物の攻撃性をなだめ、武器に訴えるより確実に、その人を守ってくれる。だから、ますます安心、信頼を深め・・・そんな好循環に入っていくと、しまいには、まるで母の胸に抱かれる赤ちゃんの無防備さ、安心してすっかり自分を明け渡し、ゆだねきった感じを取り戻し、すると、そこから燦々と放射される愛のエネルギーは最大化され・・・そうなると、
狼さえ、世話しようって近づいてくるのも夢ではなくなるかもしれない!
とにかく、その人の一挙一動に、触れるすべてのものに、愛が注ぎこまれるものだから、植物が太陽を求めるように、そこにいるすべての動植物が、近づいてくるんだ。そうしてみんな、仲睦まじく協力し合うようになる。それが、アナスタシアの「愛の空間」としての園。
生き物の協力が期待できるものだから、わずかな労働で、ゆたかな実りが期待できる。そこにいる住む人も、安心安全、しあわせに、本領を発揮できる。そんな場所をつくることができる。
それが本当のふるさとであり、家。
そんな場所をつくるのに必要なのは、愛情だけで、人工的なものは、本当に、何もいらないこと・・・
アナスタシアが唱える「愛の空間」としての菜園は、自然栽培、自給自足の農園に、一見近く見える。
違うのは、そこに住む全ての生き物とのこの一体感だろう。
たとえば、弱り切った苗だった自分を慈しみ、捨てないでいてくれた、ウラジーミルの気持ちに必死で答えようと、彼の無理解で土に入れられた化学肥料からダメージを受けたにもかかわらず、必死に花を咲かせ、たった二個のさくらんぼだけど、彼に必要な成分を天と地から集めた実りをもたらすことができた桜の木のように。
そこでは、あなたの信頼と愛に答えようとして、天と地の最上のものをあつめて、滋養のある実りをもたらそうとする植物たちが、ふんだんに育ってる。そんな園の中で、あなたはすこやかにしあわせに、また安心しきって住んでる。そうして、ますます高まる愛のエネルギーを、まなざしや愛撫のかたちで、太陽のようにふりそそいでは、それを植物たちに返す。植物たちはそれを、天と地をめぐる力と合わせ、何倍もの力へと増幅させながら、栄養や薬効が凝縮された実り、花咲く園の美しさやうっとりとさせる香りにして、返していく。
このパーマカルチャー的なシステムの中、循環しているのは、水分や栄養分以前に、愛のエネルギーだ。菜園は、その発電所。
というのも、アナスタシアのひいおじいさんによると、愛のエネルギーは、宇宙に広がり、星々に反射することで、生命エネルギーになって戻ってくる。
「愛に満ちた人間が放つ放射はその人の頭上を運行する星に一秒にも満たないスピードで届き、瞬時に反射し、再び地球に戻ってきて、生きとし生けるものに生命を与える」(『アナスタシア』33)。
生命エネルギーになって降りそそぐこの愛のエネルギーは、たぶん、ヨガでプラーナ、私たちのご先祖様が「気」と呼んだあたりのものと重なるはずだ。
ともあれ、これは植物、とくにシベリア五葉松のような大樹に多く蓄えられるというのも、彼の言。
森林浴や食、アロマなどを介して自然と触れ合うことで私たちが癒されたり、心身甦えるのは、この貯蔵分のエネルギーの放出にあやかることができるからなのだろう。
私たちは自ら愛を放射しながら、星々に反射して空から降り戻ってくるこの生命エネルギーの絶対量を増やし、これを直接吸収するほかにも、自然と深く関わることで、その貯蔵分も動員。そこからどんどん栄養を汲み取り、エネルギーを高めていくことができる。
この循環の中で愛のエネルギーが高まるほど、そこでなされる仕事は労働というよりは、コミュニケーション、コミュニオンのかたちをとり、軽やかで、楽しいものになり、生きていくのに必要なものは、労なくしてゆたかにまかなわれるようになる。アナスタシアの住む草原のように、人の手の跡がほとんど見られぬような原野状態に近づいていく。